電気通信主任技術者の資格について調べはじめると、まるで合言葉のように「難易度が高い」という言葉に出会うかもしれません。合格率の低さや、求められる知識の広さに触れた情報も多く、挑戦する前から「自分には無理かもしれない」と、少し気持ちが揺らいでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
たしかに、誰でも簡単に取得できる資格ではありません。しかし、その「難しい」という一言だけで、あなたの可能性を閉ざしてしまうのは、とてももったいないことだと思うのです。なぜなら、難しさの背景には、乗り越えるための道筋がきちんと存在しているからです。
本当に知りたいのは、漠然とした噂ではなく、その難しさの具体的な中身ではないでしょうか。そして、多くの合格者たちが、どのような壁に悩み、どのようにしてそれを乗り越えていったのか、という現実的な道のりだと思います。
これから、合格率といった客観的な数字に触れながら、多くの人が「難しい」と感じる具体的な理由を一つひとつ、丁寧に見ていきたいと思います。
合格率はどのくらい?他の資格と比較してわかる立ち位置
では、電気通信主任技術者の難易度は、客観的に見てどのくらいなのでしょうか。ひとつの目安となる合格率を見てみましょう。
この試験は、「伝送交換主任技術者」と「線路主任技術者」の二つに分かれています。総務省が発表しているデータによると、近年の合格率は、伝送交換がおおむね20%前後、線路が30%前後で推移していることが多いようです。つまり、10人が受験して合格するのは2人から3人ということになり、決して高い数字とは言えません。
他の技術系の国家資格と比べてみると、その立ち位置がよりはっきりと見えてきます。
理系の人気国家資格との比較
例えば、同じ電気系の資格で知名度の高い「第三種電気主任技術者(電験三種)」の合格率は、かつては10%を下回ることも珍しくありませんでした。近年は制度変更もあり少し高くなっていますが、それでも難関であることに変わりはありません。
また、IT業界で広く認知されている「応用情報技術者試験」の合格率は、毎回20%台前半で安定しています。
これらの資格と比べてみると、電気通信主任技術者は、理系国家資格の中でも、決して易しい部類ではないことがわかります。特に、応用情報技術者試験と合格率が近い伝送交換は、しっかりと腰を据えた対策が必要になるレベルだと考えておくとよいでしょう。もちろん、合格率はあくまで目安の一つです。大切なのは、数字に気後れすることなく、試験の中身を正しく理解し、自分に合った準備を進めていくことですね。
なぜ「難しい」と言われるのか?3つの要因を徹底分析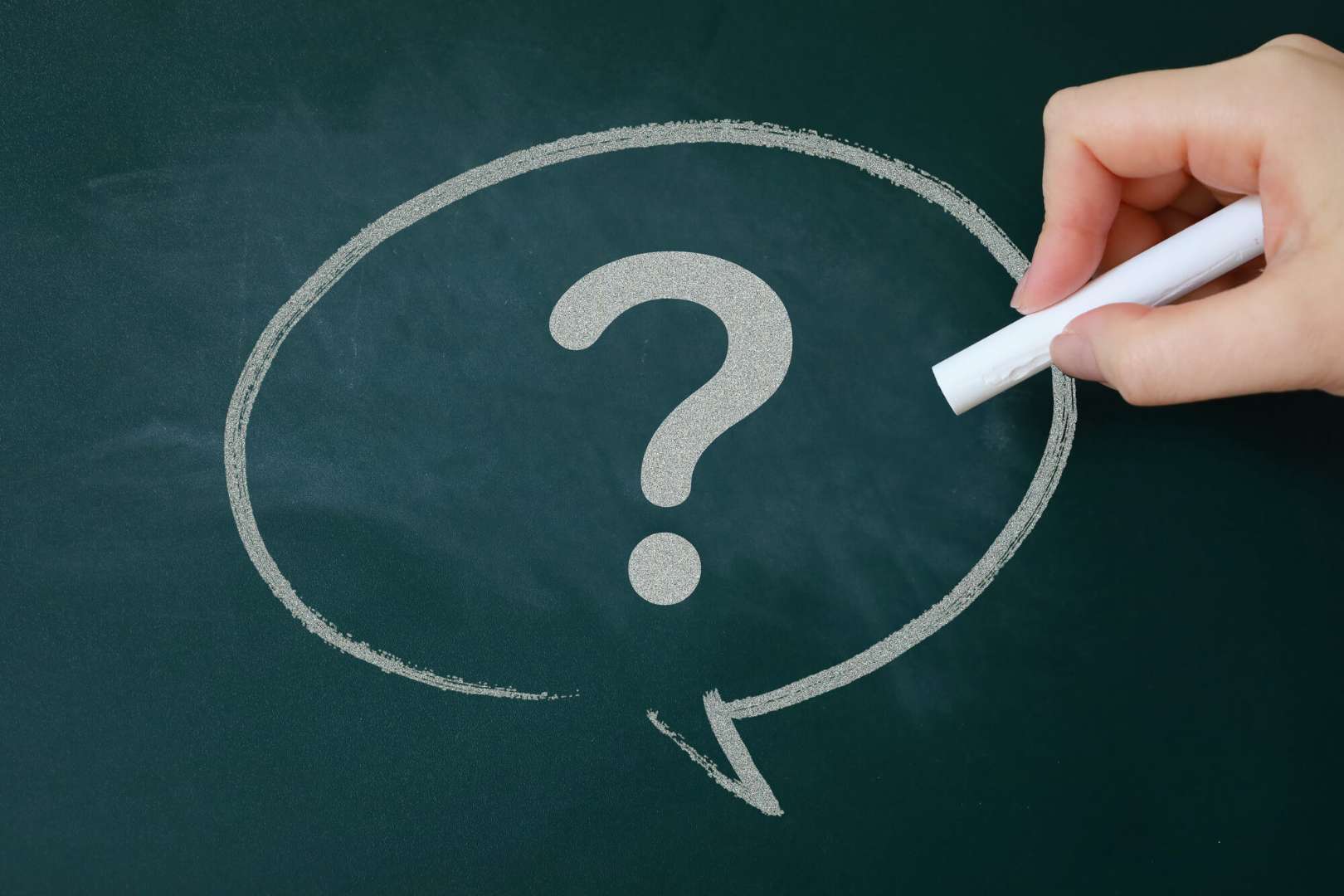
合格率だけでは分からない「難しさ」の背景には、いくつかの乗り越えるべき壁があります。多くの受験者がどこにつまずきやすいのかを知ることは、効果的な対策を立てる第一歩になります。ここでは、その代表的な要因を3つに絞って見ていきましょう。
① 端から端まで、あまりに広大な試験範囲
まず挙げられるのが、学習すべき範囲の広さです。「専門の能力」や「設備の管理」といった科目では、情報通信の仕組みの基礎から、最新の技術動向までが問われます。例えば、光ファイバー通信の原理、IPネットワークの仕組み、無線通信の技術、さらにはそれらを収容する建物の安全管理基準まで、まさに多岐にわたります。
この広大な範囲の中から、どこが重要なのかを見極め、まんべんなく知識を習得していく必要があり、多くの受験者が途中で「やってもやっても終わらない」という感覚に陥りやすいのです。
② 実務経験がないとイメージしにくい内容
電気通信主任技術者の試験内容は、実際の通信設備や現場での業務に深く関わっています。そのため、机の上での学習だけでは、具体的なイメージを掴むのが難しい場面が少なくありません。
例えば、「線路」の試験で出てくる電柱の安全基準や、地下ケーブルの敷設方法などは、実際に現場を見たことがないと、テキストの文字や図だけではピンとこないかもしれません。「伝送交換」で問われる大規模なネットワークの監視・制御についても同様です。この「イメージのしにくさ」が、知識の定着を妨げる一つの壁となっているようです。
③ 専門知識が問われる計算問題
特に「伝送交換」の区分では、計算問題が合否を分ける重要なポイントになります。対数(デシベル)の計算や、通信の品質を表す指標である「呼損率(こそんりつ)」の計算など、専門的な数学の知識が求められます。
これらの問題は、公式をただ暗記しているだけでは太刀打ちできず、その意味を本質的に理解していなければなりません。学生時代に数学が苦手だった方や、仕事で計算から長く離れている方にとっては、特に高いハードルに感じられるかもしれません。
働きながらでも合格は可能?自分に合った学習計画の立て方
これまでの話を聞いて、やはり大変そうだと感じた方もいらっしゃるかもしれません。ですが、心配はいりません。多くの合格者は、限られた時間の中で効率的に学習を進め、見事に合格を手にしています。特に大切なのは、自分自身の状況に合わせた、無理のない計画を立てることです。
まずは学習期間の目安を知る
一般的に、電気通信主任技術者の合格に必要とされる勉強時間は、500時間から1000時間ほどと言われています。もちろん、これは通信分野の知識がどれくらいあるかによって大きく変わります。
もし、あなたが実務経験者であったり、学生時代に情報通信を学んでいたりするなら、500時間程度がひとつの目安になるでしょう。一方で、全くの初学者であれば、基礎的な用語の理解から始める必要があるため、1000時間近い学習時間を見込んでおくと安心です。
例えば、平日に1時間、休日に4時間ずつ勉強するペースなら、1週間で約13時間。1ヶ月で約50時間となります。このペースで進めると、500時間なら約10ヶ月、1000時間なら約1年半から2年という計算になります。働きながらであっても、決して不可能な計画ではないことが分かりますね。
自分に合った学習方法を見つける
学習の中心となるのは、市販の参考書や過去問題集です。まずは評価の高い、自分にとって分かりやすいと感じる参考書を1冊選び、じっくりと読み込むことから始めましょう。全体像を掴んだら、ひたすら過去問題を解き、間違えた箇所を参考書で復習するというサイクルを繰り返すのが王道です。
最近では、動画で学べるオンライン講座や、学習の進捗を管理できるアプリなどもあります。通勤時間などのすきま時間を有効活用できるので、こうしたサービスを組み合わせるのも良い方法ですよ。大切なのは、自分にとって続けやすいスタイルを見つけることです。
難易度を乗り越える「環境」という選択肢
独学で学習を続ける中で、どうしても理解できない部分が出てきたり、一人でモチベーションを保つのが難しくなったりすることもあるでしょう。そんな時、忘れてはならないのが「独学だけが全てではない」ということです。合格への道を力強く後押ししてくれる「環境」に身を置く、というのも非常に賢明な選択肢の一つです。
世の中には、社員の成長を積極的に支援し、資格取得を全面的に後押ししてくれる企業が存在します。例えば、私たち株式会社建巧社もその一つです。私たちは、情報通信という社会に欠かせない分野で活躍したいという意欲さえあれば、現時点での経験や知識は問いません。入社後に専門知識を学び、資格取得を目指せる体制を整えています。
具体的には、資格取得に向けた研修や勉強会を定期的に開催しているほか、受験にかかる費用や、合格後に取得できる資格手当といった制度も充実させています。こうした金銭的なサポートは、安心して学習に集中するための大きな助けとなるはずです。
しかし、それ以上に価値があるのは、周りに同じ目標を持つ仲間や、すでに資格を取得した先輩技術者がいることかもしれません。参考書だけではイメージしづらかった現場の話を直接聞けたり、つまずいている部分を気軽に相談できたりする環境は、学習の理解度を飛躍的に高めてくれます。一人で抱え込まず、チームで壁を乗り越えていく。そんな働き方も、選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。
https://www.kenkohsha.jp/recruit
資格取得の先にあるもの。難易度を乗り越えた先に広がるキャリアとは
電気通信主任技術者の難易度が決して低くないことは、これまでお話ししてきた通りです。しかし、その事実は裏を返せば、この資格がいかに専門的で、社会的に価値が高いものであるかを示しています。
苦労して乗り越えた先には、大きな達成感だけでなく、確かなキャリアと、社会に貢献しているという誇りが待っています。この資格は、私たちが当たり前のように使っている電話やインターネットといった、現代社会のコミュニケーション基盤を守り、支えるために不可欠な存在です。その責任ある仕事に携われることこそ、この資格が持つ最大の魅力と言えるでしょう。
資格を取ることは、決してゴールではありません。それは、プロフェッショナルとしてのキャリアを歩み始めるための、いわばスタートラインです。私たち株式会社建巧社が目指しているのは、人々の「あたりまえのコミュニケーション」を支えるだけでなく、その先にある「未来のあたりまえを創造する」こと。その大きな目標に向かって、資格で得た知識と技術を存分に発揮できる舞台が、ここにはあります。


